「夢を叶える」と信じたあの日、私は鵜になった
あの頃、
私はカウンセラーになりたかった。
でも、どこを探しても「これだ」と思えるスクールは見つからなかった。
その空白を埋めるように出会ったのが、アメリカ発の心理学系コーチングスクールだった。
それが、私の中の“静かな毒”の起源になっていたと、今ならわかる。
夢は大きければ大きいほどいい。
声は通れば通るほどいい。
自己肯定感はあげればあげるほど成功に近づく。
そんな“高揚感”を輸入したこのスクールでは、
「偉大な存在になれる」という期待が、空気のように会場に満ちていた。
それは誇大妄想なのか、ただの純粋な夢だったのか、いまも判別はつかない。
アンソニーロビンズ、スティーブン・コヴィー、ナポレオン・ヒル…。
彼らの名前が飛び交う会場には、ロックスターのような講師が立ち、
「あなたも主役になれる」と繰り返し言っていた。
椅子だけが並ぶライブ会場のような空間。
音楽が鳴り響き、声が交錯し、拍手が渦を巻く。
そこでは講師だけでなく、“積極的な生徒”も舞台の一部だった。
やがて、その舞台に立った生徒たちは、
ボランティアとしてセミナー運営に関わり、
「貢献」や「成長」を報酬として与えられるようになっていった。
しかし、それは報酬というより、“手形”だった。
いつか偉大になる、いつか成功する──
その未来への手形を握りしめながら、
彼らは無償の労働に時間とエネルギーを費やしていった。
私もその一人だった。
コーチングスクールは次々に増えていった。
でも、プロとして食べていける人は、ほとんどいなかった。
なぜなら、市場がなかったのだ。
夢だけが膨らんで、現実との接点がどんどん曖昧になっていった。
スピリチュアルの特殊能力は当時、
一部の“選ばれた人”のものというイメージが強く、
誰でもアクセスできるものではなかった。
だからこそ、「誰でも資格が取れて独立できるコーチ」は
“手が届く光”のように映っていた。
でもその実態は、似たようなスキルを量産するだけ。
個性はすり減り、現場は飽和し、
気づけば誰もが「誰かの真似」をしていた。
私がいたスクールも同じだった。
カリスマ講師の周囲に集まる生徒たちは、
あたかも“鵜飼の鵜”のように、
講師のために動き、講師の思想を広める役目を担わされた。
資格を得ても、講師を越えることはほとんどない。
成長という名の階段を登っても、その階段は講師の舞台にしか続いていなかった。
そうして気づく。
この空間では、オリジナリティを出した瞬間に孤立するのだと。
自由を得たくて学んだはずの場所が、
気づけば“依存と模倣”の檻になっていた。
それでも、すべてが無意味だったわけではない。
この空間にいたからこそ得た「痛み」が、
今の私の視点を作った。
この毒を経験したからこそ、
私は独自の“視点”と“距離”を得た。
毒は使い方次第で、武器にもなる。
そのときの空虚感も、
模倣を繰り返した自分も、
誰かの影になったまま拍手を浴びた記憶も、
すべてが、今の「私の言葉」に変換されている。
拍手と熱気の中では、誰もが無敵だった。
でも、会場を出たあと、
その無敵感はふっと消えて、
私はただの、次の“導き”を求める迷子になっていた。
🌙 結びの一行ポエム
誰かの夢を支える鵜をやめたとき、ようやく自分の舟が動き出した。


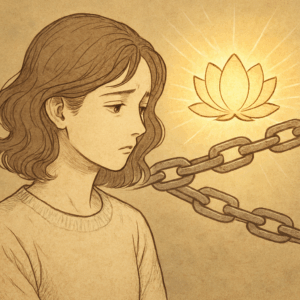
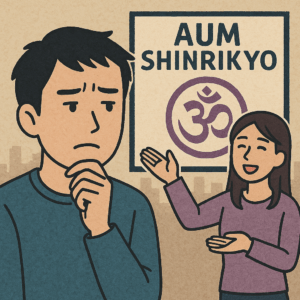
コメント